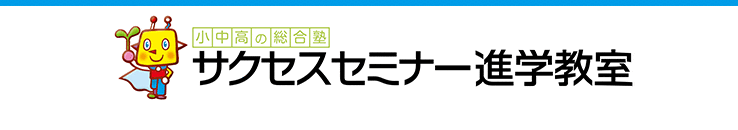登米市の「子育てにイライラしてしまってる」保護者の方へ。ゆるストイックな姿勢で向き合ってみてはどうでしょうか?

子育ての中で、「論理的に説明すればきっとわかってくれるはず」と考える保護者の方は多いのではないでしょうか。
しかし、残念ながら実際には、「正しいことを言っているのに、子どもが反発する」「納得していないように見える」と感じる瞬間があるはずです。
今回は、“論理的すぎる伝え方”がなぜ子どもの心に届かないのか、そしてどうすれば信頼関係を築けるのかを、学習塾の現場から考えてみたいと思います。
■ 論理的な説明が子どもに響かない理由
ビジネスの場面では、「論理的に話すこと」は間違いなく有効なスキルです。
ロジカルシンキングを否定する必要はありません。
むしろ、職場では論理的な人がいることで、物事がスムーズに進むことも多いでしょう。
しかし、子どもとのコミュニケーションではそれが“万能”ではありません。
論理は「過去のデータ」や「前提条件」に基づいて構築されます。
けれど、子どもたちは日々成長し、感情も環境も常に変化しています。
つまり、大人の経験則が“今の子ども”には通用しないケースが多いのです。
そして何より、子どもが求めているのは「正しさ」よりも納得感”や“共感”です。
■ 「正論」が子どもの心を閉ざすとき
「そんなこと言っても仕方ないでしょ」
「あなたのためを思って言ってるのよ」
このような言葉、つい口から出てしまうことはありませんか?
どちらも“正しい内容”ではあります。
けれど、子どもからすれば「理解されていない」「責められている」と感じてしまうこともあるのです。
子どもは正論では動きません。(大人だって、そうかもしれません…)
大人が正しい答えを提示しても、「気持ちをわかってもらえていない」と感じれば、心を閉ざしてしまいます。そして、結果として、やる気や自信を失い、「どうせママには何を言っても無駄」と思ってしまうことにもつながってしまいます。
■ 子どもの信頼を得る「論理+共感」のバランス
もちろん、論理的に考えること自体は大切です。
ただし、それを相手に伝えるときは“心”を添える必要があります。
これは意外に難しく、人生経験が豊富な方ほど、理屈で整理して話してしまう傾向があります。
親子の会話では、次のような工夫を試してみてください。
先に気持ちを受け止めてから話す
→ 子どもの感情を認めてから、必要なアドバイスをする。「どう思う?」と問いかけ、考える時間を与える
→ すぐに正解を伝えず、子どもの意見を引き出す。結論よりも“プロセス”を一緒に振り返る
→ 結果よりも、考え方や努力を認める。
こうした対話の積み重ねによって、子どもは「信頼されている」と感じ、大人の言葉が自然と心に届くようになります。
■ 「ゆるストイック」な子育てが、親子関係を強くする
最近注目されているキーワードに「ゆるストイック」という考え方があります。
これは「努力を続けつつ、自分を追い込みすぎない」という生き方です。
子育てもまさに同じではありませんか?
「こうすべき」と決めつけず、子どものペースや気持ちに寄り添いながら共に成長していく姿勢が大切です。そうした“余白”が、子どもの自立心や学習意欲を育てるのだと思います。
■ まとめ:「正しく言う」より「伝わる言い方」を意識しよう
「もっと勉強してほしい」
「もっと素直になってほしい」
「もっと自分を大切にしてほしい」
――親として、そんな願いを持つのは当然のことです。
でも、伝え方次第で子どもの受け取り方は大きく変わると思います。
私自身、熱烈塾講師として駆け出しのころ、先輩にこう言われたことがあります。
「正しいことの押し売りでは、子どもたちの心は動かないよ」
その言葉を胸に、今も子どもたちと向き合っています。
信頼関係ができて初めて、子どもは大人の言葉を素直に受け入れてくれます。信頼関係ができれば、こちらの働きかけに対して子どもたち自身が持つ力で応えるのです。
その第一歩が、“正しさより伝わること”を意識することなのです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

得意技:苦手な子ほど楽しくなる作文指導。数学的に考える国語読解。
趣味:なまはげ研究と能面