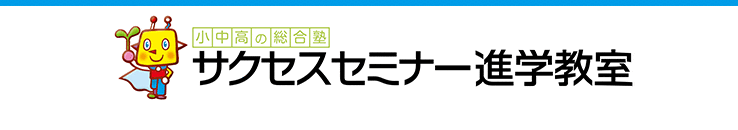自分と条件が同じ人と比べられると自己肯定感が傷つく子どもたち。
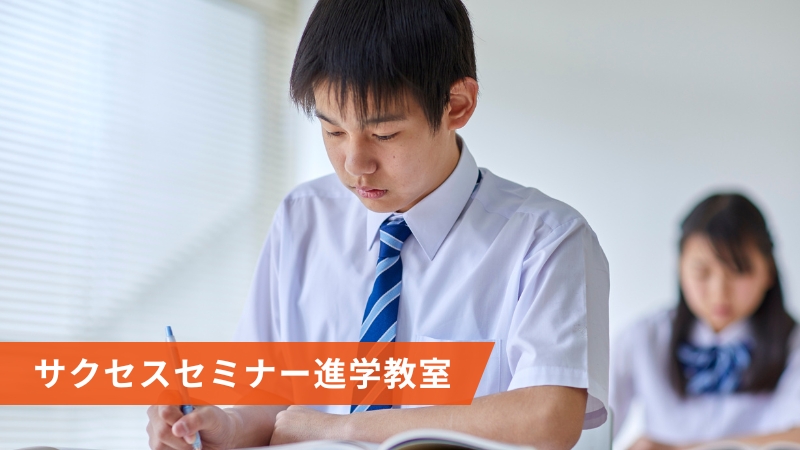
子育てをしていると、どうしても「他の子と比べてしまう」という気持ちが生まれます。成績や部活動、学習習慣など、比べる対象は数え切れないほどあります。私も小学生、中学生の頃は親の「〇〇ちゃんてすごいよね!」という言葉の裏に隠されたメッセージを徐々に受け取り、傷ついたり、一時的にひねくれ感情の嵐を巻き起こしたりしたものでした…。
お子さまの成長を見守る中で、つい口にしてしまうのが「○○ちゃんはできるのに」「△△くんは頑張っているのに」という言葉ではないでしょうか。ですが、この“身近な比較”こそが、子どもの心を一番傷つけやすいのです。
心理学には「社会的比較理論」という考え方があります。人は自分を評価するとき、どうしても身近な人と比べてしまいます。大谷翔平選手のようなスーパースターと比較されても、「自分とは世界が違う」と思えるので、むしろ憧れや目標として受け止められます。
しかし、仲の良いの同級生や同じクラスの友達と比べられると「自分と条件が同じなのに、負けている」と強く感じやすく、自己肯定感が傷ついてしまうのです。
保護者の皆さんももしかしたらご経験はあるかもしれませんね。しかし、子どもの教育に携わってる者として断言できるのは、「他者との比較」はお子さまの自己肯定感を下げ、学習意欲を損なう大きな要因になるということです。
では、どうすればよいのでしょうか。答えはシンプルです。比べるのは他の子ではなく、「過去の自分」と「今の自分」、そして「未来の自分」です。自分自身の成長を振り返り、「できるようになった」という実感を得てもらう働きかけをすることです。
サクセスセミナー進学教室 佐沼教室は、この考えを教育の軸に据えています。登米市・佐沼地区で30年以上、地域に根ざして中学生の学習指導と高校受験対策を行ってきた当教室は、知識の詰め込みではなく、お子さまが自分の成長を実感できる学習環境を大切にしています。
たとえば、定期テストの答案を返却するときには、点数だけに注目するのではなく、前回から伸びた部分や改善が見られる答案の工夫に目を向けます。「ここができるようになったね」というフィードバックは、お子さまの自信につながり、「次も頑張ろう」という意欲を引き出します。

得意技:苦手な子ほど楽しくなる作文指導。数学的に考える国語読解。
趣味:なまはげ研究と能面