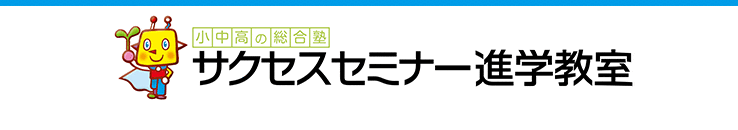国語力の土台

先日3歳の息子がこんな話をしていました。
「操縦席に乗って、レバーを引くとエンジンがかかって、お空に飛んでいくの。そして一旦着陸したら、ママのことを助けに行くね。」
妄想でもしていたのでしょうね。
幼児と会話をしていると、彼らの想像力や感受性の豊かさにいつも驚かされます。
そして「え、一体いつそんな表現を覚えたの?」と親の方がドキッとするような新しい単語や表現も、自然な文章の中で活用していたりするので、これまた感心させられてしまいます。
昨今は「考える力を育てよう」とか「論理的思考力を身につけよう」などと言われています。どの時代においても「考える」という行為こそが人間たらしめるものなのだと思います。
まず最初に触れておきたいことは、『考える』という動作を行うためには『言葉』が必要不可欠だということです。日本語でも英語でも他の言語でもです。
言葉を使わずに、つまり語彙力がない状態で考えることは出来ません。言葉が考えを生むのです。
また同じ事象を経験していても、持っている語彙力によって表現が変わります。すると考え方も変わります。
料理で例えれば、語彙力は材料です。材料が豊富であればあるほど、様々な料理を振る舞うことが可能になります。
高い国語力があってこそ、深い思考が可能となることは言うまでもありません。
小中学生の勉強においては国語力が全教科の基盤となりますので、国語力を磨くことは全教科の成績向上に繋がります。
社会に出て仕事をする上でも、人間関係を築き上げるのにも、やはり考える力や発信する力は必要になりますね。
言い換えれば、人生を豊かにする鍵は国語力にあると言えるのではないでしょうか。
※文科省では以下の4つの力を国語力の中核としています。
「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」
では、これらの力をどのように育てればいいのでしょうか。
お子さんは誰しもが、これらの能力を開花させる種を持っています。 しかし、その種を開花させるには水や日光を与える必要があります。それは大人の役目です。お子さんの国語力は、家庭でのコミュニケーションが土台となります。(親でなくても、親身になってくれる大人からの働きかけが重要)
「●●しなさいよ」など一方通行の指示ばかり発してしまっている家庭では、自分で考える力というのはなかなか鍛えられません。
そこで、国語力を伸ばすために家庭でできる取り組みをいくつか紹介したいと思います。
①子どもにとにかく話させる
1日の出来事、学校や習い事で学習したこと、経験した出来事を本人の言葉で表現させましょう。
一日を振り返って出来事を整理し、言語化する練習になります。
ここで注意が必要なのは、聞く側の姿勢です。
途中で遮って話したり、非難や否定をしないで傾聴を心がけましょう。
一度否定されると、話したくなくなるのは大人も同じです。安心して話したくなる雰囲気づくりも大事です。
また聞き方も、クローズドクエスチョン(Yes/Noで答えられる質問)よりもオープンクエスチョン(自由に回答できる質問)にすると会話が広がりますよ。
②言葉遊び
学びは「楽習」。楽しむことがミソです。
休日など空いた時間に家族で楽しみながらお子さんの国語力を磨いてあげましょう。
・カルタ
ことわざ、慣用句、四字熟語、都道府県、国旗、歴史上の人物など様々な種類があるので、お子さんの年齢や興味に応じて関心のあるテーマから導入してみましょう。お子さんにオリジナルかるたを作成させてみるのも良いですね。
・古今東西ゲーム
テーマに関連する言葉をリズムに合わせて順番に言うゲームです。
お子さんが興味をもっているものや学習内容に応じてテーマを設定してみましょう。特別な道具が必要ないので車の中でもいつでもどこでも楽しめます。
③家族で読書感想文
1冊のノートを用意し、家族で順番に読書記録をつけていくというもの。
感想文と言っても継続できるように1行~3行程度の短いものからスタートしてみましょう。読書習慣をつけるためにも小学生のうちから楽しみながら取り組むのがおすすめです。親子でお互いにどのような本を読み、どう感じたのか、何を考えたのか、ということがまた会話のきっかけにもなります。
子どもたちは親の背中を見て育ちます。これは紛れもない事実です。学校や塾で新しい知識を学習しますが、その勉強の土台となる国語力は家庭で育まれます。
是非ご家庭でお子さんとのコミュニケーションの機会を積極的に増やし、お子さんの考える練習の機会を作ってあげてください。親子の関係が深まるだけでなく、お子さんが充実した人生を切り拓く力になることと思います。